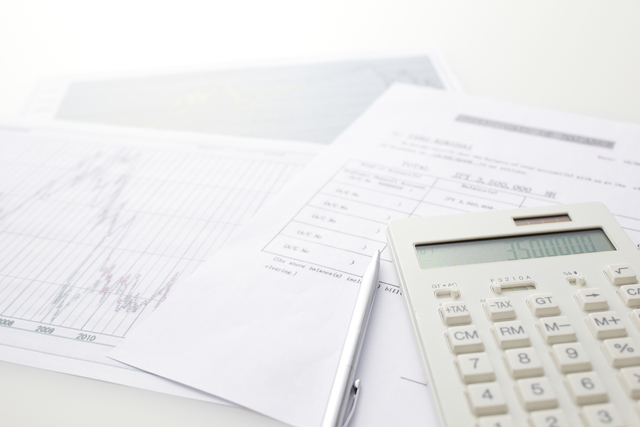豊富な経験をもつ司法書士や行政書士をお探しなら
〒355-0221 埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷409-10
受付時間:平日10:00~18:00(事前予約で時間外・土日祝日の相談可)
初回無料相談実施中
お気軽にお問合せください
お気軽にお問合せください
0493-59-9681
名義変更(相続)

まずは遺言書の有無の確認を
「相続の基本について」
お客様からのお問い合わせでよく「不動産の名義を変更したい!」というご連絡をいただくのですが、不動産の名義(所有者)を何の原因もなくただ「変える」ということはできません。そこには贈与であったり、売買であったり、何らかの「原因」がなければなりません。その一つが「相続」です。
「まずは遺言書の有無の確認を!」
相続では被相続人の意思が尊重されます。ですので例えば「甲土地を、長男Aに相続させる」旨の遺言があった場合は、原則甲土地はAが相続することになります。また、遺言書がない場合に、被相続人である夫の法定相続人として、妻、長男、二男の3名がいるケースにおいて、その三者間で夫の遺産である建物を妻が相続するという内容の遺産分割協議がまとまったら、建物を妻の単独名義にすることができます。
相続人と法定相続
遺言書や死因贈与契約書がなく、遺産分割協議も行わない場合は、お亡くなりになった方(被相続人)の①子ども、子どもがいなければ②直系尊属(父母、父母がすでに他界している場合は祖父母)、直系尊属がいなければ③兄弟姉妹の順序で遺産を相続します。なお被相続人の配偶者がいるときは、配偶者は常に相続人となります。(ただし、相続放棄の申述を家庭裁判所に行い申述が受理されたときは、その方は初めから相続人でなかったものとみなされます。)具体的な相続分は下表のとおりで、これを法定相続といいます。
法定相続分
| 配偶者以外(①or②or③)の相続分 | 配偶者の相続分 | |
| ①子ども | 計2分の1 | 2分の1 |
| ②直系尊属 | 計3分の1 | 3分の2 |
| ③兄弟姉妹 | 計4分の1 | 4分の3 |
③で、兄弟が何人かいる場合は、亡くなった兄弟の両親とどちらか一方の親が異なる兄弟は、同じ両親から生まれた兄弟の2分の1の相続分となります。
代襲相続
相続を考えるうえで忘れてはならないのが、代襲相続です。代襲相続とは、被相続人の子どもが、被相続人が死亡する以前に死亡していた場合に、被相続人の子どもの子(被相続人からみて、孫)が相続人になることをいいます。
さらにその孫に子がいる場合(被相続人からみて、ひ孫)で、被相続人の死亡する以前に、その子どもと孫も死亡していた場合にはどうなるでしょうか?その場合にはそのひ孫が相続人になります。これを「再代襲」といいます。
なお、③の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、代襲相続は認められますが、再代襲は認められません。つまり代襲相続が認められるのは、被相続人からみて、甥、姪までということになります。
相続と登記
例えば、亡くなった夫の不動産を売りたい、贈与したいと思ったときに、被相続人である夫の名義のままで処分することはできません。所有者である夫はすでに亡く、そこには不動産の名義人である夫の売りたい、あげたいといった意思は存在しません。ですので、あらかじめ相続人に名義を変更しておかなければなりません。
また、下表のケースではどうでしょう。
法定相続分
| 被相続人A | ||
| 長女B | 二女C | 三女D |
| 長女E、F、G | 二女の子H、I、J | 三女の子K、L、M |
※各々の配偶者はすでに死亡しているものと仮定する。
例えばAの不動産を遺産分割で単独名義にするには、Aの死亡時B、C、Dの三者間の話し合いで済んだものの、そのまま放置してB、C、Dも死亡してしまったら、今度はE、F、G、H、I、J、K、L、Mの九者間での協議が必要になってしまいます。血縁関係も徐々に薄れていき、協議自体がまとまらなくなってしまう可能性が高くなってしまいます。各々に配偶者がいたらなおさら揉めることにもなりかねません。
このような事態を防ぐためにも、速やかに相続登記を済ませることが望まれます。
※民法改正により相続登記は義務化されました。当事務所では開設以来多くの相続に関する登記業務を行ってまいりましたので、お気軽にご相談ください。
その他のメニュー
お問合せはこちら

お気軽にお問合せください